THE LAST HUMAN
ザック・ジョーダン
2020
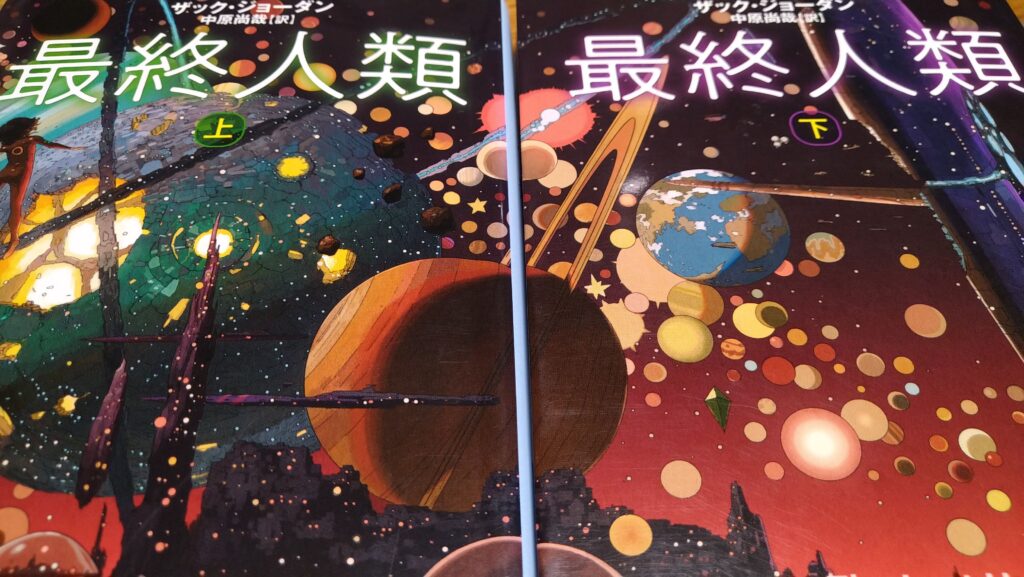
読み始めて真っ先に思ったのは、シュライクに育てられている人類の娘、というもの。シュライクは「ハイペリオン」(ダン・シモンズ、1989)に登場する時を超越する殺戮者。真っ黒い外骨格を持つカマキリのような異星生命である。主人公のサーヤは、異星種族のウィドウ類のシェンヤによって育てられている人類の娘。ウィドウ類はシュライクにそっくりなのだ。もちろん、殺戮者ではなく、ネットワークを形成する知的種族のひとつであるが、その闘争本能は強力である。このウィドウ類のシェンヤが人類であることを隠すため希少なスパール類として登録し、守り育っているのがサーヤである。
読み進めるうちに感じたのは「百億の昼と千億の夜」。光瀬龍が1965年~1966年に雑誌連載し1967年に単行本化されたSF小説である。そして萩尾望都が光瀬作品を原作に1977年~1978年に雑誌連載した同名の漫画作品である。
本作「最終人類」には「神」は出てこないが、その世界観や雰囲気は萩尾版ときわめて似ていると感じたのだ。生命の躍動と空しさ、仏教用語的には色即是空空即是色のようなことだ。
読み終わってよくよく思い返してみると、後半に出てくる主人公サーヤの「仲間たち」の構成が「オズの魔法使い」(ライアン・フランク・ボーム、1900)の主人公ドロシーの仲間たちとそっくりだということに気づく。すなわち、ブリキの木こり、臆病なライオン、案山子である。気がついてちょっとほのぼのする。サーヤもドロシーがそうであったように魔法使いではないが高次の存在にだまされたり、裏切られたりしながら選択するしかなかったのだ。
さて、印象はともかく、作品についてまとめていこう。本作「最終人類」はザック・ジョーダンのデビュー作であり、最終刊行まで4年半、執筆数250万語を経て約13万語の作品として発表されるに至った。
物語の世界は銀河系のネットワーク世界。10億以上の星系、140万以上の知的種族のほとんどすべてが参加している巨大な社会である。第二階層以上の知性があれば法的人格権が認められ、それ以下であれば法定外の人格となる。それは自然生物、人工物に関わらず、知的レベルのみで判断される。運搬ドローンにも衛生施設にも知性はあるが法定外、というわけだ。そして、この世界で人類はネットワーク世界の許されざる敵であり、遠い昔に絶滅した種族である。
しかし、人類にも生き残りがいて、主人公のサーヤは自分が人類であることを知っていた。人類だと知られた途端に狩られる存在になることも。そのために、ネットワーク社会の基本であるネットワークに全感覚で入るためのインプラントも入れられず、間接的なコミュニケーションツールでの限定的ネットワーク利用しかできずにいた。知的にも法定人格は認められても最底辺の仕事しか与えられない、そんな未来がすぐそこにあった。仲間を探したい、自由にネットワークにアクセスしたい、人類と名乗りたい、サーヤの思いは募る。
母であるシェンヤはサーヤを娘として認識し、そのすべてをかけて守ることを本能的に誓っていた。
やがて事件は起こる。そして人類としてのサーヤが発見され、彼女は生きるための戦いに巻き込まれるが、それは大きな大きな大きな壮大な陰謀の幕開けでもあったのだ。
このネットワーク社会は、階層社会である。サーヤを含む第二階層の知的存在には第三階層の思考の早さ、深さは想像も付かず、ネットワークでの「みえる」「できる」レベルも格段に異なっている。ましてその上の第四階層、ネットワークそのものは時空への操作も含めてその能力や行動の意味は第二階層にとって想像することさえ難しい。外で走り回る蟻は気にならないが、家の中でうろうろしてきたら殺すか外に出してしまう。その蟻にとっては人間のそういう気まぐれは理解も想像もできないだろう。そういうことだ。
そして、サーヤはネットワーク宇宙のひとつの役割を負わせられる。報酬は「人類」。
ヴァーナー・ヴィンジの「遠き神々の炎」にも似ているかな。
好きです、こういう話。でてくる集合知性オブザーバ類にはちょっと閉口するけれど、どこかで似たようなやつ(ら)を見たり読んだりした記憶があるのだけれど、オリジナルがどれか分からないので、これは実際に読んだ人への宿題ということで。