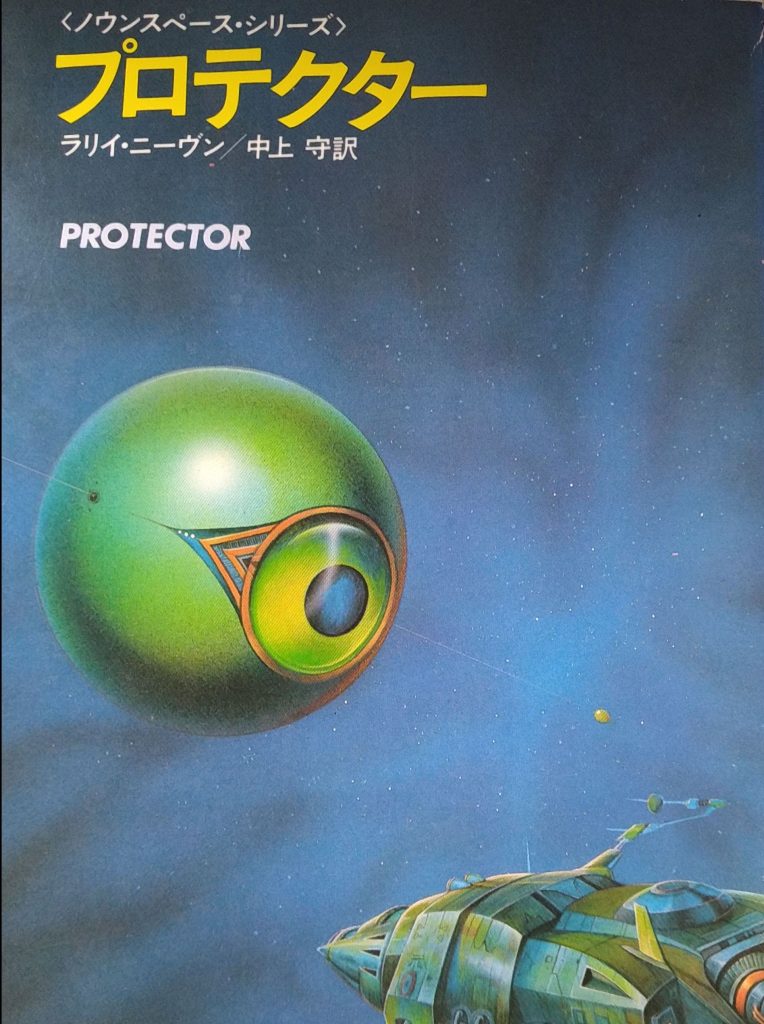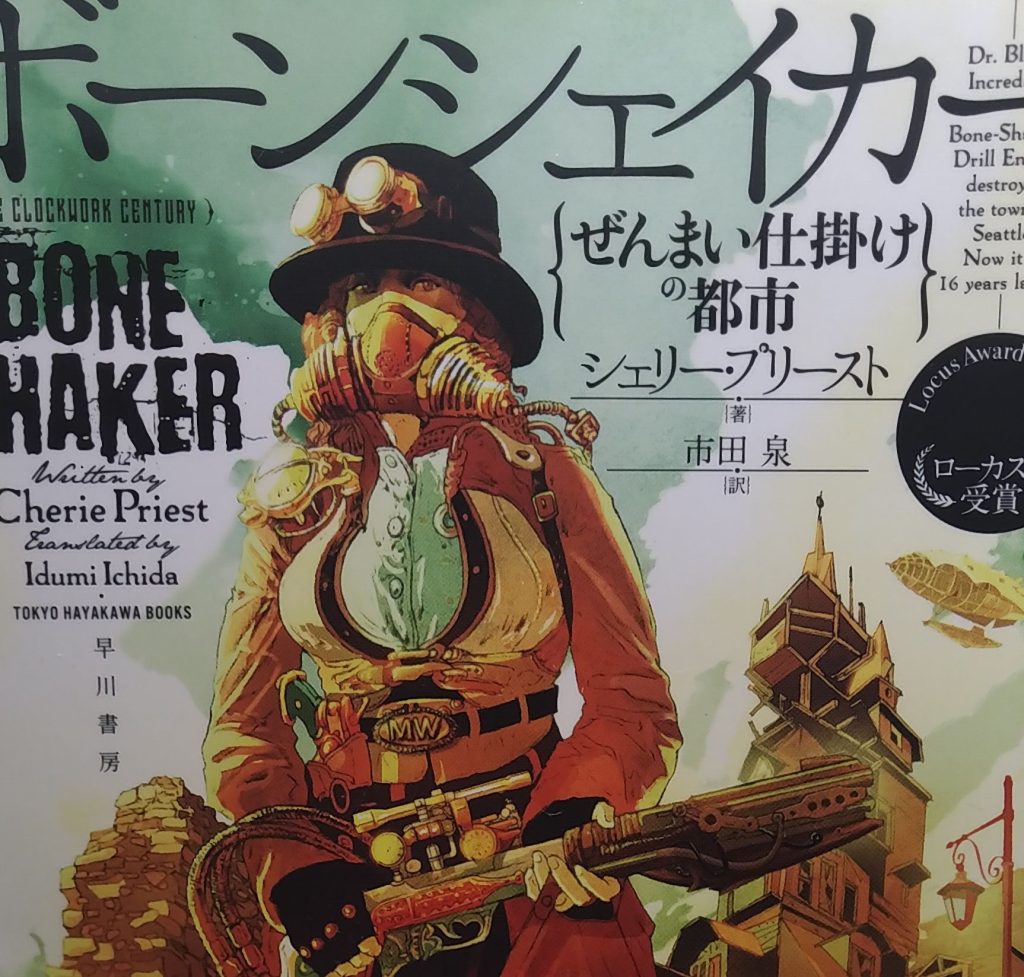内さま http://uchisama.com/
2006年11月からインターネット配信番組としてはじまった「内村さまぁ~ず」。テレビ朝日系の深夜バラエティ番組「内村プロデュース」(2000年4月~2005年9月)の終了をうけて企画されたもの。当初はネット配信のみで、配信元もミランカ、内さま.comをはじめ様々な配信サービスで行なわれてきました。2009年からはMXテレビ等での再編集放送なども始まっています。2015年9月からはamazon primeが配信先となり、タイトルも「内村さまぁ~ず SECOND」に変更されました。2022年10月の#404でさっくりと最終回を迎えてしまいます。amazon primeとの契約更新がされなかったのか、また配信先を探すのか、再開はあるのか、これまでのアーカイブをamazon primeは続けてくれるのか? なんとか続けてほしいものです。
ところで、DVD化もされていて毎回3本ずつ出されており、各3作ずつ収録されています。2022年3月の最新版でVol.88を数え、累計で100万枚、2012年の40巻の時点でギネス記録にも認定されているのです。なお、第1巻は初年で3万部を超えていると配信中で報告されています。
私は、現在は地上波テレビは見ないし、他のバラエティ番組も見たいと思わないのですが、このシリーズだけは楽しみにしています。
今日的なコンプライアンスや価値的に問題になるものもあり、特に時々ある水着の女性の扱いは、どうなのかな、と思います。それらを除けば、力の抜けただらだらした動画で、だらだら感を笑いに変えられるところが実に良いのです。ドランクドラゴンの塚地さんも言っていましたが、見てもみなくてもよくて、ゆるいからこそ、疲れずに見ることができるというのが最大の特徴です。もちろん、いくつかの回には大笑いもあります。でも、そんな期待はしていないのです。同世代で芸能人として生きる人たちが、普段着的に楽しそうだなあと思うだけです。
さて、個人的に好きな回をピックアップしていきます。たくさんあります。
なお、健康診断回、有吉さん登場回、ダチョウ倶楽部回、ito回については最後にまとめています。それ以外は時系列。
2007.4 #11 何でも選手権!(イジリー岡田)
イジリーさんが頭真っ白になって呆然。
2007.4 #12 俺達!激写隊(有野晋哉)
「さまぁ~ず内村」の回。大喜利会。
2007.5 #13 俺達ちょいとムチャするぜ!2(キャイ~ン)
内村組のキャイ~ンと戯れるロケもの。内村さんの自家用車がいじられる回。
2007.6 #15 俺達そこそこアクターズ!!(アンガールズ)
スタジオでのシチュエーションもの。その後定番となる内村顔芸登場。
2007.6 #16 我ら、初老べからず!!(レッド吉田)
内P組のレッド参戦。全員40歳代にさしかかり身体的変化を老眼や片足立ちなどで自覚する回。それだけなのに、おもしろい。
2007.10 #23 東京喫茶店はしご旅(ビビる大木)
人気企画の1回目。「さぼうる」登場。そして、5年ぶりのビビる復活。
2007.11 #25 大自然クイズ(児嶋一哉)
のちの定番企画の第一回目。企画はさぐりさぐりだけれど、本気のクイズ大好きで熱くなる3人がみもの。
2008.7 #41 008年夏を先取り!愛車を徹底的に洗おうぜ!!(土田晃之)
内P時代にさんざんどっきり企画に使われた三村の愛車を掃除するだけの回。ほんとうに掃除するだけなのに。
2008.8 #44 江戸東京博物館巡りツアー!(バナナマン)
2022年4月から3年間大規模改修工事に入り休館となっている江戸東京博物館、その魅力をたっぷり? 本当はくいついて見学したいのに、そうはいかないバナナマンとの企画。やっていることは中学生男子。
2009.1 #54 さまぁ~ずのコンビ結成20周年を笑いナシで祝っちゃう男達!(千秋)
2008年に20周年を迎えた大竹と三村の足跡をたどるのんびりした回。
2009.5 #62 フリップその全てを知りたがる男達!(バカリズム)
後半の「顔文字」を使った大喜利大会が楽しい。
2009.8 #68 とにかく休みは欲しいけど いざ休みになると何をしたら良いのかよくわからない男達!(アンタッチャブル)
何もしない回。撮影用のレンタルハウスで5人がただただだらだらする回。俳優さんたちが数名でトークやミニゲームをするようなファン向けの番組はあるけれど、おじさんたちがそれをやるとこうなる。
2009.9 #69 町のサウナ屋さんぶらり旅(ビビる大木)
さまぁ~ずの裸祭り。サウナですから当然脱ぐ。内村笑う。
2009.12 #75 明日からイライラしないで過ごす男達!!(つぶやきシロー、ふかわりょう)
ふかわさんが入ることで、内Pなつかし感。最後には大喜利大会も。
2010.5 #85 老後の為に自分の体を知っておきたい男達!!(土田晃之)
神回。のちに何度も再現される「(だめ)だめ男」の登場。2007.6の#16以来の体力測定。40代は身体の衰えを自覚する時期か。
2010.6 #87 木本を待つ男達!!(木本武宏)
どんな大物ゲストでもやれるのではないか?という企画。地上波を見ないので知らないのだが、近年深夜にやっている「紙さま」という番組にも似たコンセプト。タイトル通り、不在の木本を待つ。木本の内さま別名「久保」初登場。
2010.7 #89 私・鳥居みゆきの扱いに少々困っている男達!(鳥居みゆき)
鳥居さんはその後レギュラー企画を持つのだが、初登場ではがっつり3人とからみ、3人が本気でぐったりする。舞台稽古で疲労気味の内村がさらに疲れる。
2010.7 #90 光良を待つ男達!!(オアシズ、有吉弘行、岡田圭右、狩野英孝)
舞台本番中の内村さんを待つさまぁ~ずと5人。いなくてもいないからこそ存在感のある男。2010年でもっとも視聴された回とか。
2011.2 #103 念願の場所でロケをする男達!(柳原可奈子)
ラーメンライスが食べたい!という柳原さんの願いを叶えるために、ラーメン店で大喜利、ゲームを繰り広げる4人。#101からは16:9の画角。
2011.2 #104 若手の得意分野を色々と知って たまに遊びたい男達!(キングオブコメディ、インスタントジョンソン)
若手紹介企画の最初の方。内Pさながらの大喜利大会。
2011.4 #108 全員守るべきモノができた男達!(レッド吉田)
大竹さんが結婚したことで、子だくさんのレッド吉田さんが「家族」について企画を用意。ふだん聞けない家族の話が次々に。
2011.6 #112 これからを見据えてナイツのテリトリーに入っておきたい男達!(ナイツ)
漫才協会理事で内村さんの事務所の後輩ナイツがお年寄りに受けるためのコツを3人に伝授。笑いもありますが人間の勉強になる。
2011.7 #113 来たるべき大竹一樹の結婚式が心配で心配で仕方がない青木達!(青木さやか)
異色回。ちょっと青木さやかさんが変。ウェディングドレスを着てテンション上がりっぱなしで、目が飛んでい…。
2011.11 #122 5人揃えば潰しが利く男達2011!!(バナナマン、さがね正裕)
このあとの回で何かあるたびに引用されることが多い回である。ここで内村さんが笑いのために右手首を痛め、その後完全な回復がない状態になる。#121と2本取りの2本目で全員疲れている中、異様にテンションが高く、怪我しがちな条件が整っていた。バナナマン、さまぁ~ずとの組み合わせは内P時代にも三村さんが膝を怪我するなど無理しがちなところがある。笑いのためだが悪い相乗効果だった。
2012.1 #125 僕・狩野英孝の2012年を何が何でも成功に導きたい男達!(狩野英孝)
お笑い芸人になるわけではありませんが、勉強になります。テロップ大喜利も。
2012.3 #129 俺達、さらに絆を深めちゃうぜ!(天野ひろゆき)
「企画で家電製品を買う」というだけですが、家族会議なしに購入するとなると本気で悩みます。その姿を淡々とお楽しみください回。
2012.6 #135 ちょいと一杯ひっかけたい男達!!(東京03)
極めて不真面目で、ある意味真面目な回。3人に収録前に酒を飲ませてお笑いの本音を聞き出そうとするという企画。酔っていいと言われれば飲むのが3人。果たして飲ませて良かったのか、お笑いの勉強にもなりますが。
2012.8 #139 屋台で懐かしい芸人としっぽり語りたい男達!!(ヒロシ、ダンディ坂野、長州小力、ゴルゴ松本)
おもしろいかどうかは別として、それぞれの芸人さんの仕事、生き方が垣間見える回。そしてゴルゴさんがバビル2世に。
2012.8 #140 今日ぐらいは照れずにパパの顔を存分に見せちゃう男達!!(土田晃之)
前年のレッドさんの企画に続き、大竹さんに第一子が誕生したことから、今回は子ども4人の土田さんを迎え、最初から最後まで家族トークのみの企画。笑いよりほのぼの優先。
2013.2 #152 内さまと相性が良いのは塚地なのか僕なのかをどうしても決めたい鈴木達!!(ドランクドラゴン)
前回の#151(バカリズム)の回で行なわれたパントマイムクイズ企画、ひとりだけが内容を知っていて、もうひとりがその内容に合わせて一緒にパントマイムをやり、内容を把握できていたかを問うもの。芸人の「伝える」能力の高さを知る。
2013.5 #158 中岡・谷田部の収録に対する姿勢をもっと前向きにさせたいコカドと坪倉とゆかいな仲間達!!(ロッチ、我が家)
やさしいプチドッキリ企画で笑える。
2013.7 #162 東京スナックはしご旅!!(ビビる大木)
「はしご旅」シリーズ。今回は都内のスナック3件。当然飲む。飲めば酔う。相手は酔客に慣れたスナックのママ。プロとプロの会話が秀逸。
2013.10 #168 無駄なく効率よく尚且つ面白い内村さまぁ~ず!!(原口あきまさ)
「企画中はノーカット」の条件でいくつかの企画を行なう。将棋、デッサン、トーク、耳かきなどなど。最後は本気の剣道。
2014.1 #175 可愛くて大好きな山根の結婚を照れずに積極的にお祝いしてもらいたい山根達!!(アンガールズ山根)
収録の頃に結婚した山根のお祝い会。めでたさを笑いに変える。
2014.2 #177 谷田部の結婚式を勝手にクイズにして参加した気になりたい男達!!(我が家)
山根に続き谷田部の結婚。こちらは坪倉撮影の結婚式プライベート映像を元に。
2014.2 #178 冬の東京にいながらにして、より少しでも南国気分を味わい、それを思い出に残しておきたい男達!!(木本武宏)
過去もっともハードなロケ。タレント、スタッフともに全員グロッキー。
2014.3 #179 先輩方から芸能界で生き残るコツを教わりたいハマカーンと後輩達!!(
フレンチブル、ハマカーン)
収録後半の「他人のものボケを全力でやる」企画初回。その後、ときどき出てくる企画ですが、いずれもとてもおもしろい。
2014.5 #185 超マジメなアンバランスを芸人として面白く再生してあげたい土田達!!(土田晃之、アンバランス)
中堅ながらなかなか活躍の場が得られないアンバランスのふたり。プチドッキリなどをしかけながら笑いのツボを探る。
2014.07 #189 尊敬する内村光良50回目の誕生日をグアムで楽しく祝いたい後輩達!!(
ウド鈴木)
2回目の海外ロケ企画。海外がうれしくて楽しそうにはしゃぐ。
2015.2 #204 有望な若手芸人の引き出しをガンガン開けたい男達!!(しゃもじ、キサラギ)
若手養成企画。大喜利、マイム、コントなどなど、たまにある内P的な内容。
2015.4 #208 伊集院とラジオを通して遊んでみたい男達!!(伊集院光)
ラジオ界の大御所となっている伊集院さんを迎え、ラジオコントの企画。地味でもほのぼの楽しい。
2015.5 #210 大先輩に追いつけ、追い越せ!今、伸び盛りの若手芸人達!!(流れ星、Wエンジン)
若手(中堅)養成企画。ぐだぐだ企画に穴埋め大喜利、内P的内容に、まじめな笑い論まで。
2015.11 #223 今回のロケを全てめくりに任せちゃう男達!!(バカリズム)
ここから「内村さまぁ~ずSCOND」となり 配信元がAmazonPrimeビデオとなる。特に内容に変更はない。
2016.4 #234 なんにも知らない鈴木拓をこっそり転がしながら遊んじゃう男達!!(鈴木拓)
ときどきある「裏企画」。表側の企画とは別に3人が裏企画で遊ぶというもの。鈴木拓プレゼンの裏でドミノ。
2016.4 #235 最近のインパルスと堤下の事情を知ってほしい板倉達!!(インパルス)
いろんな事情で初期の再配信なし、DVD収録なしの吉本興業所属芸人。Amazon配信になったことでやはりなんらかの事情によりこの回よりしばらく何回か吉本芸人が登場する。最初は内Pでも常連だったインパルス。
2016.7 #241 座卓の可能性を探りたい男達!!(品川庄司)
内P時代の常連登場。「座卓を使って遊ぶ」という男子小学生たちがやりそうなことを一生懸命やっては笑いに変える。
2016.8 #242 内さまと車座になって語り合いたいあの時の芸人達!!(パラシュート部隊、 髭男爵、X-GUNさがね)
内Pで華々しくデビューしたパラシュート部隊が凱旋、語る。
2016.10 #247 映画監督・内村光良を影ながら支えたいオレたち内村組!(ウド鈴木、インパルス・板倉、三四郎・小宮)
映画「金メダル男」(監督・脚本・主演、内村)の番宣的ではないが番宣の回。大喜利ます。
2017.1 #254 八百屋さんで1時間楽しんじゃう光浦達!!(オアシズ光浦、アンタッチャブル柴田)
内村休みの回。すなわちさまぁ~ず。
2017.4 #261 3人揃えば最強だと自負している男達!!(東京03)
内さまトリオとのトリオ対決。身体を張ってる。
2017.5 #263 今に始まった事じゃないけれど塚っちゃんの仕事の割合が俳優業に寄り過ぎているので芸人の勘が鈍っていないか細かく確かめたい鈴木拓!!(ドランクドラゴン)
内P会。わざとらし王に大喜利に、芸人引き出し王も。
2017.6 #265 初老だらけの超優しい陸上競技大会!!(岡田圭右)
2回目となる競技大会。バッティング王・岡田の伝説のはじまりです。
2017.7 #267 内さまの3人が身近な人達に照れずに「ありがとう」といってほしい勝俣達!!(勝俣州和)
中華料理店で4人が褒めあう。心に響けばポイントが。
2018.1 #279 新春ひねり出しかくし芸大会!!(ロッチ)
2017年の紅白総合司会がいじられる。
2018.1 #281 惜しまれながらも今年で閉店するお店はしご旅!!(ビビる大木)
恒例企画のはしご旅、今回は閉店するお店。ほのぼの回。
2018.3 #284 季節外れだけどこたつの良さの違いを痛感したい男達!!(千秋)
こたつを使って遊びます。
2018.3 #285 クイズで知るコカドの哀愁人生に同情して愛おしくなっちゃう男達!!(コカドケンタロウ)
ロッチのコカドさんは幼少から苦労している。実は大竹さんも。そして大喜利。
2018.8 #295 塚っちゃんの良い所を存分に引き出してドランクドラゴンの危機を回避したい鈴木拓!!(ドランクドラゴン)
大喜利あり。
2018.8 #296 超大自然クイズ直前!緊急強化会議!!(狩野英孝、TKO木本)
超大自然クイズファンならば必見。過去のクイズのすべてが明らかに。
2018.10 #300 我社の伸び悩む若手中堅芸人達をバーターで内さまに出演させたいハマカーン!!(ハマカーン、ビックスモールン、どきどきキャンプほか)
2018.11 #301 内さま300回記念を遅れ馳せながらお祝いしたいよゐこ達!!(よゐこ)
濱口が仕切り、有野が料理。思い出映像も。
2019.1 #306 新春ひねり出しかくし芸大会!!(ロッチ)
2年続けての同企画。2018年も紅白総合司会がいじられる。
2019.2 #308 西村とやすの無人島生活をクイズで楽しんじゃう男達!!(バイきんぐ西村、ずんのやす)
裸祭りです。やすが結婚したいと泣きます。
2019.5 #315 カミナリ一家を堪能しながらカミナリのコトを好きになっちゃう男達!!(カミナリ)
ときどきある「家族エピソード」もの。芸人実家のみなさんは明るい。
2019.7 #318 歯を治したことが芸人としてプラスしかないと気づいて欲しい和樹と浩信!!(三四郎の小宮 ずん飯尾)
印象を変えるために歯の治療をしたふたりプラス三村さん。赤裸々に語りますが、後半はぐだぐだな対決です。
2019.7 #319 内さまの3人に家庭持ちの良さを教えてもらいたい佳代子とあさこ!!(大久保佳代子、いとうあさこ)
赤裸々語り会。3人の家族のエピソード。笑えるけどほっこりします。
2019.7 #320 今こそ内さまに恩返しがしたいパラシュート部隊!!(パラシュート部隊)
内Pで事実上デビューした当時20歳のパラ部。内P後は福岡で活動し、いまや40歳。がんばっています。
2019.10 #326 いつの間にか阿佐ヶ谷姉妹マニアになれちゃう殿方さま~!!(阿佐ヶ谷姉妹)
3人が座って芸人のプロフィールやあれこれを大喜利しながら聞く会。このパターンは時々あるけれどゲストMC側のおもしろさが秀逸。阿佐ヶ谷姉妹だから。
2019.11 #328 内さまと一緒にものまね大喜利を繰り出したいものまね芸人達!!(原口あきまさ ほか)
原口さんの第二弾企画。2本取り前後編でものまね芸人が変わりものまねをします。その後たびたび使われる名言「そんなつもりで家を出てきていない」が初登場します。
2020.2 #335 過去最高にキレキレの武雅を体験してもらいたい塚地の武雅!!(ドランクドラゴン)
肉体を絞って体重も落とした塚地さんとの対戦もの。すでに古傷だらけの3人が無理したり、無理しなかったりします。
2020.4 #338 第7世代の勢いに負けちゃいけないとマネージャーが持ち込んだ企画に対して「何その心配!?」だったらやってやろうじゃないかと逆に奮起する三四郎とその同期達!!(三四郎、アルコ&ピース)
レジェンドから最新芸人まで芸の世界を語ります。
2020.6 #342 TKO木本のプライベートクイズを通して僕のコトをもっと好きになってくださる男達!!(木本武宏)
この回からリモート収録。初なので3人完全分離で行なわれます。パンデミック時代の試行錯誤開始。そして、TKO木下不祥事の後。まだ木本さんの出来事の前ですが…。
2020.6 #343 ようこそここへ! バーチャルスタジオ! 東MAXランド THE REMOTE!!(東貴博)
いつもは体育館で身体を張る「ランド」企画。リモートでできることを探ります。3人が同室仕切りありに変わります。
2020.7 #345 今度こそちゃんとVTRの続きを観て欲しいアンガ田中とワタナベエンタ芸人達!!(アンガールズ田中)
同企画の2回目。パンデミック前にリモートのような企画をしていたので、その続編。田中さんが罰ゲームでとんでもないハプニングに見舞われます。
2020.8 #347 超大自然クイズ直前! 第2回緊急強化会議!!(ずんのやす、スピードワゴン 小沢)
過去の「大自然クイズ」の記録を辿りながらこれからのクイズを考えます。
2020.10 #352 ボウリング大会を開催して大好きな女子プロボウラーの世界を知ってもらいたい素人ボウラー土田!!(土田晃之)
ソーシャルディスタンスが生んだ新たな試行錯誤の1作。3人のプロボウラーが登場し、4人のおじさんたちが身体を張って芸をします。内Pを彷彿させるどうでもよい感じの笑い回。
2020.12 #356 祝!結成30周年!よゐこの思い出クイズを通して僕らのコトを楽しく祝ってくださる男達!(よゐこ)
ウンナンと縁の深いふたりの30年をクイズで楽しむ。人に歴史あり、よゐこに南原あり?
2021.1 #359 唯一のホームである内村さまぁ~ずで思う存分やりたいコトをやりたいペンギンズクラブ!!(ペンギンズ、マツモトクラブ)
相談あり、クイズあり、ゲームあり。若手と3人が気楽に遊びます。
2021.2 #360 相方へのお悩みクイズを通してコンビ間の溝を埋めてもらいたい納言の幸じゃない方とラランドのサーヤじゃない方!!(納言、ラランド)
神回です。後半、大喜利大会で若手のひとりが内さまの導きで一気に成長します。お笑い私塾。
2021.2 #361 今日は私達のコトを知ってもらったり、相談したり、色々と教えてもらったり、とにかく3人にお近付きさせて頂きたいAマッソの加納と村上!(Aマッソ)
内村さんいじりの回になりました。
2021.4 #364 クイズを通して僕らの知られざる頑張りっぷりを知って頂きたいネバーギブアップ芸人達!!(スギちゃん、長州小力、ビッグスモールンのチロ、X-GUNさがね)
時々ある懐かし芸人回。ビックスモールンの話は心を打つ。
2021.5 #368 おじさん達もまだまだ若い子には負けないぞ!打倒!日向坂46!!恒例の体に優しいスポーツ対決(岡田圭右、日向坂46から3人)
アイドル初参戦で「終わりが近いのか?」と多くの人たちが不安になった回。
2021.7 #371 祝!結成30周年!キャイ~ンの思い出クイズを通して僕らのコトを楽しく祝ってくださる男達!(キャイ~ン)
よゐこの30周年(#356)に続く、うんなんファミリー30周年もの。懐かしい話が続出です。
2021.7 #372 THE・芸人騙し合いバトル!!(ビビる大木、ハナコ)
内P時代のバトルロワイヤルの改変版だが、大ベテラン3人対若手3人はちょっと若手に不利なのだった。
2021.8 #373 内さま3人と一緒に大喜利企画をやらせてもらいたい日向坂46!!(わが家・坪倉由幸、日向坂46から3人)
バラエティに慣れたアイドル3人との大喜利大会。意外とうまいのでおもしろい。
2021.9 #375 永野presents!今日から僕の妹分ももクロと仲良くなって下さる男達!!( 永野、ももいろクローバーZから3人)
ももクロまで登場。こちらもうまいこと大喜利やゲームで楽しめます。
2021.11 #379 第2回THE・騙し合いバトル!!(東貴博、納言・薄幸、乃木坂46から3人)
アイドルを迎えてのだまし合い企画。シチュエーションコント的な要素も加えて、可能性をみせてくれます。
2021.12 #382 活躍する場はテレビだけじゃない!今こそ内さまとラジオで楽しみたい男女達!!(アルコ&ピース、乃木坂46・新内眞衣、フリーアナウンサー赤江珠緒)
2015年の#208伊集院光以来のラジオコント回。コント性が高くなっています。
2022.1 #384 今日だけはコントについてとことん語り合って下さる男達!!(ハナコ)
コントトリオがコントの大先輩と真面目に語り合い、真剣にコントを繰り広げます。よい回。
2022.2 #386 私達も内さま3人と一緒に大喜利企画をやらせてもらいたい日向坂46・1期生達!!(日向坂46から3人、ロッチ・コカド)
アイドルを入れた大喜利会2回目。ゆるい感じの大喜利です。
2022.3 #388 結局の所、鳥居みゆきについてまだまだ何も知らない男達!!(鳥居みゆき)
鳥居みゆき回5回目、1本が前衛芸術映画のようになっている。
2022.3 #389 今日だけはとことん夫の話を聞いてほしい芸人の妻達!!(安めぐみ、近藤千尋、和泉杏)
安めぐみ降臨! 内P後期のアシスタントとして数多く出演していた「めぐのやす」が登場。異色の回で、笑いもあり、最後は号泣する人も…。
2022.4 #390 老後の為に自分の体を知っておきたいおじいちゃん達と元アイドル達!!(土田晃之、横山由依、北原里英、野呂佳代)
AKB48の元メンバー3人を加えた体力測定企画。12年前の同企画からどれくらい体力が落ちているのか。ついに「おじいちゃん」扱いになった3人。
2022.5 #393 モグライダーと内村さんの架け橋になりたい狩野とさまぁ~ず(モグライダー、狩野英孝)
内村の後輩若手を使って内村さんをいじる回。
2022.8 #399 大喜利休んじゃってごめんなさい!名誉挽回して内さまのご機嫌を伺いたい草薙航基とその相方!!(宮下草薙)
396、397はたくさんの若手芸人が登場する大喜利バスツアー。ところが、草薙は大喜利が苦手で本気で逃げてしまう。そこで反省とリベンジの回。もちろん、大喜利はやらない。
2022.9 #400 超大自然クイズ直前! 第3回緊急強化会議!!(ずん)
三村休み回。ということで400回の区切りは過去のクイズ大会の総まとめ。いろいろ3人の個性と特徴がでてきます。
●健康診断
内村プロデュース時代にも何回か行なわれた健康診断企画「そろそろ人間ドックで体の不安を解消したい男達!」、2008年より定番となる。最初のうちは「食道炎」程度で大騒ぎしていたがだんだん年をとっていくと告げられる病気(可能性)も深刻なものに。内村はこの結果をうけて喫煙をやめたが、三村、大竹は止める気配がない。解説役の医師が2回を除き同じ方で、一緒に年をとっていく感じがよい。2011年には内村が完全に禁煙する。2014年には三村が禁煙宣言する。2018年は三村の重病可能性があり精密検査で配信遅れる。三村は禁煙する。2019年、三村8カ月で禁煙中断。医師嘆く。2020年は大久保さんが濃厚接触者で電話出演に。三村の体調を医師が本気で不安がる。2021年は三四郎・小宮、アシスタントで登場した織田いちかさんが病気を読み上げる声と抑揚が実によい。あとは平穏かな。
2008.12 #52(日村勇紀)
2009.12 #76(出川哲朗) 神テロップ回。
2010.12 #99(つぶやきシロー)
2011.12 #123(出川哲朗)
2012.12 #147(つぶやきシロー)
2013.12 #172(鈴木拓)
2014.11 #198(澤部佑)
2015.10 #222(TKO木下、MCは木本)
2016.10 #248(ケンドーコバヤシ)
2017.12 #277(イジリー岡田)
2018.12 #304(東京03豊本、MCは角田)
2019.12 #330(狩野英孝)
2021.1 #358(オアシズ大久保…欠席、MCは光浦)
2022.1 #383(小宮浩信)
●有吉再生・再ブレイク
2007.12 #27 有吉の単独ライブを成功させよう!
再ブレイク直前の有吉。内Pの縁が有吉を蘇らせるか。
2008.7 #42 ザ・有吉弘行MCへの道!トークパラダイス
再ブレイクに入った有吉のMCおためし企画がある。
2010.4 #84 本当は有吉の様に思う存分毒を吐きたい男達!
地上波人気芸人となった有吉の本領発揮、過去2回とはまるで違う「こなれた」有吉の姿がある。
2015.9 #219 映画俳優風な仕事の合間にちゃんとお笑いの顔もお届けしたい有吉とレッド達!!(有吉弘行、レッド吉田 ほか)
映画の取材対応で忙しい3人を有吉が翻弄する。大喜利も。
2020.3 #336 どんなコトでも縛りさえあればたちまち面白くできちゃう男達!!(有吉弘行)
5年ぶりの有吉さん、TVバラエティ司会者として「まわし」が手慣れています。冠番組持ちの4人がただ小学生のように遊びます。後半はシチュエーションコント、内Pです。
●上島竜兵を笑い、偲び、そして
2007.12 #28 年忘れ!かくしていた芸大会
3人と上島さんがひねりだす「かくしていた」芸。ババロアを取り分けます。
2009.10 #72 今こそ上島竜兵という男について真剣に考える安田達!
上島さんがリーダーとしての飲み会「竜兵会」が盛んだったころのこと。
2015.4 #209 寺門ジモンに5人掛かりで勝利してとにかく黙らせたい男達!!
3人そろう初企画。ジモンと身体を張って対決します。
2019.8 #321 ここ最近の上島竜兵を内さま3人に知ってもらいたい土田晃之!!
プチどっきりで、居酒屋で後輩芸人と飲む姿をながめます。内さまの「良い人生だ」「もうすぐ死ぬのかな」という言葉が今となっては寂しく聞こえます。
2020.9 #350 結成35年のダチョウ倶楽部に1mmでも興味を持ってもらいたいダチョウの竜兵!!
5年半ぶりに3人揃って登場。トリオがお互いの不満を出しては語る内さま人気企画の真打ち登場。ソーシャルディスタンスで芸の多くを奪われた3人が、本気で語ります。すごく笑えるけれど、いまとなってはちょっと寂しい。
2021.4 #365 祝!還暦 とにかく上島竜兵をお祝いしたい男達!!
最後の出演回。後半3人がスライドショーを見て芸人としてちょっと感動します。
2022.10 #403 NEWダチョウ倶楽部を引き出したい内村さまぁ~ず!!
ふたりになったダチョウ倶楽部。最終回前の特別な回になりました。
●itoにはまる3人
2021.3 #362 おもちゃの国!宮下パークで童心に帰って遊び尽くしてほしいおもちゃマスター宮下!!(宮下草薙)
特筆すべき内容ではないのですが、グループ協調型カードゲームの「ito」初登場、3人がはまります。
2021.3 #362宮下草薙会でitoを知った3人。とくに内村。大喜利的な要素があり競争ではないところがはまった原因か?
直後 2021.3 #363の吉住、ドランクドラゴン鈴木拓回でも後半itoで遊ぶ。
そして、2021.5 #367では「第1回itoだけで乗り切っちゃう男達!!」と題し、TKO木本、三四郎小宮に加え、モデルの滝沢カレン、DJ松永というこれまでにないタイプのゲストを招いてゲームのみの回を行なう。
2021.06 #370第2回(バナナマン、ぺこぱ、久間田琳加)
2021.10 #378第3回(ラランド、生見愛瑠、本並健治)
その間に#374でもitoをやっている(宮下草薙、Aマッソ)
パンデミック下の特殊事情も加わり、よいコンテンツを見つけたということではなかろうか。itoをゆるいバラエティ番組に仕立てたコツはそのテーマ設定にある。