THE SPEED OF DARK
エリザベス・ムーン
2003
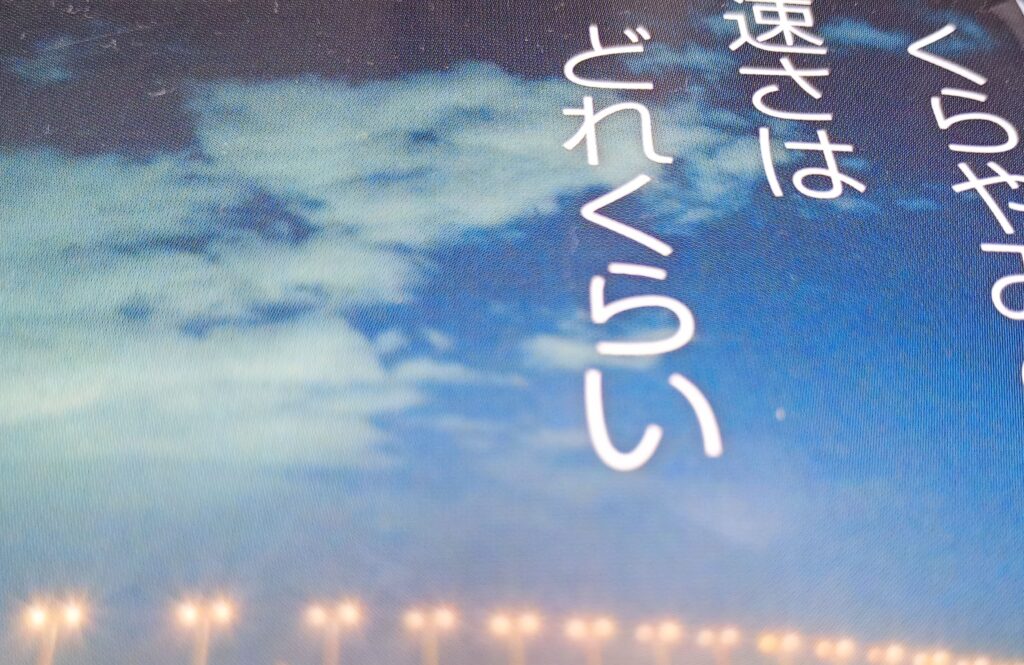
エリザベス・ムーンといえば、「若き女船長カイの挑戦」の5部作中3作がすでに訳されている。続編を楽しみにしていたのだが、その後翻訳される気配はない。残念。こちらは同時期に訳されたネビュラ賞受賞の作品だが、エンターテイメント色の強い宇宙もののミリタリーSFである「若き女船長カイの挑戦」とはまったく趣の異なる作品である。
長いこと自分の中での課題図書であった。だって「感動の21世紀版アルジャーノンに花束を」なんて釣り文句が書かれているのだから、心が落ち着いているときでないと読みにくいではないか。年齢を重ねるにつれて「重たい」話に弱くなってくるし、少し避け気味になってしまっている。
そうはいっても、課題図書。読みました。もちろん、読んで良かったです。良いことは分かっているのですから。どうして良いことと分かっているのに、そうやって理由をつけて避けてしまうことがあるのでしょうか。自分ではままならないのでしょうか。そうして今読む選択とはなんでしょうか。その動機は?わかりません。60年生きてきても、自分の選択の動機や理由などは分からないものです。分からないなりに、選択し、それはなるべく後悔しないで済むように心がけているだけです。難しいですね。
さて、本書の舞台は近未来、自閉症(こんにちでいう「自閉スペクトラム症」)が出生前に「治療」できるようになった社会である。とはいえ、比較的新しい技術であり、出生前治療ができる前に生まれたのだが、一定の治療を踏まえて支援体制があれば、その知的特徴を生かした高度な知的労働を行なうことで、「ノーマル」な人たちと変わらない収入を得ることができる人たちもいる世界である。ちなみにここで「治療」とか「ノーマル」とか表現をかっこつきで表現しているが、21世紀初頭の現実の世界では障害のあり方や程度も様々であり、支援の必要性の幅も異なる。また障害であっても一方でそれは個人の特質という面もあるので、小説の中の表記を、その全体像抜きにここで記載すると違和感や誤解につながるかもしれない。
作者のエリザベス・ムーンは時間をかけて執筆当時での当事者や支援者、研究者などとの長いやりとりを行い、本作を書き上げている。
その成果はていねいに自閉症と社会のあり方や、主人公のルウ・アレンデイルという魅力的な主人公に現れている。
自閉症のルウ・アレンデイルは、製薬会社で持ち前のパターン解析能力を生かして働いている青年である。中級クラスのアパートメントで一人暮らしを満喫中。クラシック音楽を聴き、車を運転し、趣味は古典的スタイルのフェンシング。対人関係には困難はあるが、自分のライフスタイルを変えなければさほど問題はない。最近はフェンシングの仲間の女性とそこはかとない相思相愛になりつつある。
しかし、ルウの周りが少しずつ騒がしくなる。直属の上司はルウたち自閉症のチームに理解があるが、新しく転任してきたさらに上のボスは経費の無駄だとして彼らを排除しようと考えた。動物実験ベースで出生前ではなく成人後に脳を薬剤等でいじることにより自閉症の対人関係困難な状況を改善するという治療法を彼らに試そうと画策する。
一方、フェンシングの仲間の女性との関係は少しずつ縮まり、また、大会に出てそのパターン解析能力によるフェンシングの能力の高さを披露した結果、陰湿な犯罪被害を受け始めることになる。いやおうなく新しい状況と新しい対人関係にさらされていくルウ。
ボスが強制的に進める治験について詳しくなるためルウは苦手だと思っていた生化学について独学をはじめる。そしてルウは少しずつ「変わり」はじめる。そんなルウの選択とは。
タイトルの「くらやみの速さはどれくらい」とは、光と光のない「くらやみ」についての話である。くらやみは光より常にその先にあるということは、くらやみはもしかしたら光よりも早いのではなかろうか、という問い。含蓄深いね。
これは全体を読んでからの話だけど、文庫版で503ページからの第18章のおわり、「ピザにのせたアンチョビ」をめぐる自己認識についてのルウの自問自答がある。2ページ以上にわたり、アンチョビが好きな自分とアンチョビが嫌いな自分をめぐり、実に、実に、実に読み応えがある。もうこれを書きたかったのではないかと思うぐらいによい文章だ。
実はここにいたるまで、一章一章ゆっくりとしか読み進められなかった。激しい展開があるわけでなくSFではなく状況描写的な普通小説としても読めるので夢中に読み進めるというより一章読んではちょっと頭で整理を付けて、という感じだったのだ。でも、途中でやめずに良かった。良作。「アルジャーノン」も名作だけど、全然違う。これは人格、自己認識と「選択」の物語だ。
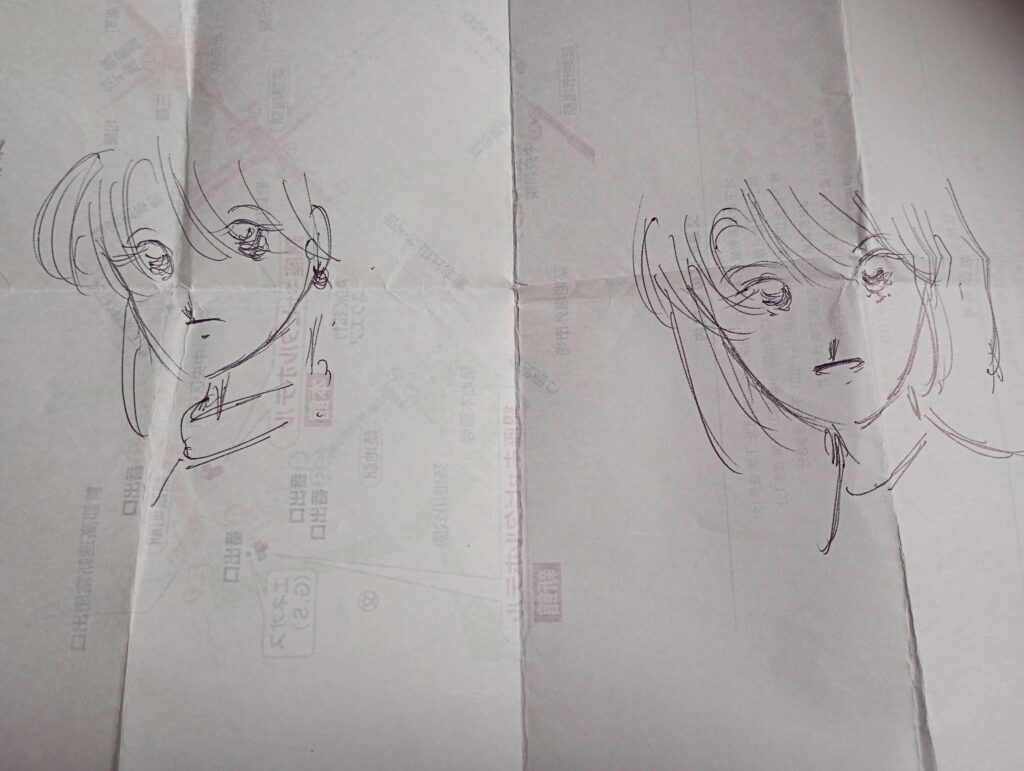
余談。本書は古本店で手に入れたのだが、都心のホテルの案内図をプリンタで打ち出したA4の紙とその裏にボールペンで書かれた女性の漫画的スケッチが2枚描かれていた。古本を手に入れるとときおりこういうことが起きる。多いのは航空券の半券や本のレシート、本屋さんのしおりなどだが、ときにはメモのようなものがはさまっていることもある。本への書き込みはちょっと困るが、こういうのは少し楽しい。この人は、この本を持ってどこかから都心の(ちょっといい)ホテルに泊まったのだろうか。そうして一人でこの落書きをしたのか、それとも誰かが書いたのか。この本はどこで手放したのだろうか…。どんな気持ちでこの本を読んだのだろうか。考えるのも少し楽しい。